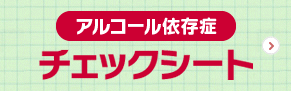回復のカギ
自分はもう酒は飲めないということを、なかなか受け入れられなかったけれど。
K・I 断酒2年(男性・40歳・内装会社勤務)
飲むための嘘が増えていく

初めて専門病院に入院したのは、36歳のときです。「飲みすぎだから週2回は休肝日を作って」と言っていた妻が、ついにインターネットで専門病院を調べ、その日に病院と連絡を取ったのです。数日前から連続飲酒のような状態になっていた私は、フラフラのまま病院へ連れて行かれました。
ケースワーカーと面談を行ない、「もう飲むことはできませんよ」と言われたときは、意味が分かりませんでした。体が治ったらまた飲める、そう思っていたからです。その後の診察で、医師に「両手を挙げてください」と言われ、挙げたその手の甲の上に1枚の紙を置かれました。私の手の震えが紙に伝わり、紙が大きく揺れて落ちました。それを見た医師は、「アルコール依存症です。あなたはもう一生分の酒を飲んでしまいましたね」と言いました。その瞬間、大粒の涙が勝手に溢れてきました。
もう酒を飲めない体なんだということ、生活を変えなければいけないということ……。それを受け入れることができるようになるまで、1年以上かかりました。
私の酒に対する執着は、20代後半から強くなっていったように思います。朝から酒のことが頭に浮かび、「飲むための嘘」が増えていきました。「コーヒーを買ってくる」「タバコを買ってくる」と言ってコンビニへ行き、1カップを買ってその場で飲む。それでも足りなくて、夜中トイレへ行った後にこっそり出かけて、コンビニを2、3軒回って1カップを体に流し込む。合計すると、1日に1升は飲んでいて、そのくらい飲まないと、落ち着けなかったのです。
内装の仕事でも、だんだん影響が出るようになりました。仕事だけはきっちりやろうとしていたのに、遅刻が増え、脚立から落ちたり、監督に「酒臭いから帰れ」と言われたり。社長にも「おまえ飲みすぎじゃないのか? ちょっと控えろ」と指摘され、そのときは反省するのですが、すぐに「飲んで何が悪い」と考える自分がいました。
手の震えが出てきたとき、アルコール依存症だった父が、「朝から飲むと字がすらすらかける」と言っていたのを思い出しました。確かに自分も、飲むと手の震えが止まる。けれども、自分は父と違いきちんと家庭を守っているし、アル中ではない。そんなふうに騙し騙し飲んでいるうち、ついに入院となったのです。
入院しても、いつも飲む理由を探していた
入院生活の最初のうちは、離脱症状に苦しみました。体が落ち着いてくると、深刻さが薄れてきて、飲んでも何とかなるのではと考えるようになりました。院内飲酒で強制退院になった人がいたので、さすがに病院で飲むのはまずいと思い、自由時間に近くのスーパーでノンアルコールビールを買って飲むことで飲酒欲求を紛らわして、ひたすら退院の日を待ちました。自分には養わなければいけない家族がいるから、こんなところにはいられない、と。
退院後は1ヵ月半毎日通院し、職場に復帰しました。日々飲酒欲求が高まっていくのがわかりました。そんな折、仕事の段取りに関して社長とトラブルがあり、それが引き金となり何もかもから逃げたくなりました。
飲みたい、逃げたい……。とにかく誰も知らないところへ行きたくて、携帯を置いたまま家を出ました。コンビニで焼酎の5合パックを買い、その日は公園で一晩明かしました。翌朝、一度行ってみたかった場所へ行き、公園で飲み、次にまたどこかへ行こうと思って駅で駅員に話しかけたところまでは覚えています。目覚めたら、病院のベッドの上でした。 私は倒れて救急車で運ばれたそうです。妻が捜索願を出そうと警察に行ったちょうどそのとき、連絡先を見つけた救急隊員から妻に連絡が行ったということでした。
翌日、退院したその足で、妻と二人で主治医のところへ行ったときは、入院を勧められると思っていました。けれども主治医は「入院しますか? 通院しますか?」と選択肢を出してくれ、仕事を続けながら通院することを選びました。ところが、抗酒剤を処方してもらい、これで酒をやめようと思った矢先、かつての入院仲間と電話で話し、「I君なら節酒でもいけるんじゃない?」と言われたその一言で、気持ちが180度変わってしまいました。
電話を切った瞬間、コンビニに足が向いていました。結果的に、前よりもっとひどい飲み方になってしまい、2度目の入院となりました。
2度目の入院のきっかけになったのは、社長の言葉でした。一緒に出かけたとき、「明らかに前のような動きになっている。飲んでるだろう」と言われ、ついに会社を休んだとき、家にやってきて、「もう1回入院しなよ」と勧められたのです。実は妻が病院のケースワーカーに相談していて、社長に協力してもらって介入する段取りを整えていたと、後になって知りました。
酒をやめよう、断酒会へ行こうと思えるまで

なかなか断ち切れなかった酒への未練が少しずつ解けてきたのは、不思議ですが、最初の頃に受けていた毎日の点滴のおかげでした。なぜ飲んだらいけないのか、なぜ自助グループが必要なのか。点滴をする間、看護師さんが話す言葉が少しずつ耳に入ってくるようになり、だんだんと心が素直になっていくのを感じました。
だったら断酒会に行ってみようかなと思い、病院から毎日通いました。そこで家族の人たちの体験談を聞いたとき、初めて我に返りました。自分もこの人たちが言うのと同じようなことをしてきて、妻子を傷つけてきたんだとわかり、自分は断酒会に行かなければいけない人間なんだと、ようやく受け入れることができたのです。
退院する前日、断酒会に入会しました。断酒会の会員であるという形があれば、それが自信になって酒をやめ続けていけるような気がしました。例会に出る中で、自分は飲んだらいけない人間なんだという感覚ができてきて、自分の中が少しずつ変わっていったように思います。家の近くに酒の自販機があるのですが、それもだんだんと自分には関係のないものなんだと思えるようになっていきました。
とはいえ、半年後の年末、出張先のホテルで1度再飲酒しました。1週間の長い出張だったので、ケースワーカーさんとも相談し、夜は現地の断酒会へ参加することにして会場の地図もプリントアウトしてもらっていたのに、毎日帰りが遅くなり、だんだんと断酒会へ行くことを考えなくなっていたのです。そしてホテルのエレベータの前にあった自動販売機のフロアで、最後の夜にチューハイを1本買ってしまいました。
1本くらいいいだろう、飲むなら今しかないと思ったら止まりませんでした。真っ赤になった自分の顔を鏡で見たとき、やってしまったと我に返りました。年明けから断酒会の先輩とあちこち出かける約束をしていたことや、病院の新年例会に出るつもりだったことを思い出して青くなり、そのまま布団にくるまって無理やり寝ました。
出張から帰ってきても、飲んだことを誰にも知られたくない、言わなければバレないと考える自分がいました。けれどもみんなを騙していることが心に重くのりかかり、10日くらい経って「実は飲んだ」とまず妻に告白しました。その後、主治医、ケースワーカー、周囲の人たちにも告白し、断酒会でも「スリップしました」と話しました。最初のうちはしんどかったですが、あちこちの断酒会へ行って話すうち、少しずつ自分が解放されていくのを感じました。
酒は日常のどこにでもあります。気が緩むと手を出す自分がいることに改めて気づかせてくれたのが再飲酒でした。あれから2年が経ちます。かつてあれほど頭の中を占めていた酒のことは、今はまったくと言っていいほど頭に浮かびません。酒をやめて良かったのは、子どもたちや妻と普通の会話ができることです。笑いあうこともたくさんあって、飲まなかったらこんなに楽しい会話ができるのかと驚きます。
家族は、「飲んでいたときは最悪だった。飲んでいない方がいい」と言ってくれます。職場でも、「その方がいいな。ちゃんと仕事してくれるようになったな」と言われます。だから、このまま変わらず、普通の生活を続けていきたい。飲まなければ、それができるのです。
- 回復のカギ
- ●妻が病院や上司と連携し介入した
- ●入院中の看護師との会話
- ●断酒会で聞いた家族の体験談
※写真は本文とは関係ありません