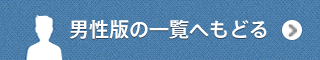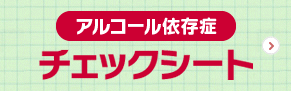回復のカギ
10年間止まらなかった酒が、断酒会で止まったのは、そこが自分の居場所だと思えたからだと思う。
Y・K 断酒17年(男性・64歳・団体職員)
酒が睡眠薬とガソリン代わりだった
16年前、断酒会で断酒1年の表彰を受けたときのことです。事務局長さんに「1年大変だったろう」と言われました。けれども本当に不思議ですが、私には大変だったという印象がありませんでした。36歳で依存症と診断され、10年間酒が止まらなかったのに、本腰を入れて断酒会に参加したらスムーズに断酒が続きました。毎日例会に行きさえすれば、温かく迎え入れてくれる仲間がいて、リラックスできるし飲酒欲求もわかず安心できる―。私にとって断酒会は、心の居場所だったのだと改めて感じます。
アルコール依存症は、孤独になっていく病です。飲んでいくことによって、家庭や職場で居場所を失っていきました。私は大きな労働組合の職員をしており、若いときは仕事に生き甲斐を感じていました。何かを主張するのは苦手ですが、飲めば頭がすっきりして企画書もすいすい進むし、先輩と議論をかわすこともできる。ところが役職が上がっていくと、いろいろなことが見えてきて矛盾やジレンマを感じるようになり、気持ちを押さえ込んだまま仕事と酒量だけが増えていきました。

飲み方がおかしくなったのは、34歳で選挙活動を担当してからです。毎日3時間しか睡眠がとれず、乗り切るための緩和剤とガソリン代わりになったのが酒でした。飲めばストレスが消えてリラックスできるし、元気が出る気がしました。そうして怒涛の3ヵ月を乗り切り、選挙が終わったときには抜け殻のような状態になっていました。
単調な事務仕事に耐えられず、目標を見失った脱力感から無気力になり、ますます酒にのめり込みました。「風邪です」「疲れました」と言って会社を休む一方で、子どもたちの学校のPTA活動や子供会など、地元の集まりには積極的に関わっていました。「子どものためだ」「みんながやらないから俺が引き受ける」と言いながら、自分が満たされた感じがしたし、堂々と飲む口実にもなっていたのです。
妻に酒のことを注意されても、「俺はこれだけやっている」と屁理屈をこねて黙り込ませ、聞き入れませんでした。家にも職場にもいたくなく、罪悪感からますます深酒になる悪循環。ついに降格されてしまい、それまで築いてきたものがすべて崩れた気がしました。
「飲んではいけない」と思うほど、飲みたくなる
ガンマGTPの数値が高く、保健師の指導で入院し、断酒会を勧められましたが「俺は違う」と拒否しました。連続飲酒に陥り1週間無断欠勤をし、上司が家に訪ねてきて精神科入院となったのは、36歳のときです。アルコール依存症と診断され、飲酒運転をしないよう車のキーも金も妻に預けましたが、同僚に金を借りたり定期預金を崩したりして、その後も10年酒が止まらず入退院を繰り返しました。
あの頃、夜が待ち遠しかったのを覚えています。飲んではいけないと思うほど飲みたくなり、妻が眠った頃を見計らい、ワンカップと金が隠してある草むらへ行くのです。人には見られたくないので近くの公園のトイレで飲み、浅ましい自分が嫌になりました。けれども酒を一口体に入れると、そんなことも忘れてしまうのでした。
体がつらくなると入院し、退院するとまた隠れ酒をしていた私が、方向転換をする最初のきっかけになったのは、医師に「断酒会の人が年一回の健康診断に来るから会ってみなさい」と勧められ、仕方なく会ったことでした。顔を見るなり「あんた飲んだろ」と言い当てられ、衝撃を受けました。それが心の奥にあった「このままではまずい」「どうにかしたい」という気持ちを引き出してくれたのか、それから私は飲みながらでも、断酒会に通うようになったのです。
当時、地元の病院のベッドがいっぱいで、私は実家に帰り通院をしていました。治療を終え地元に帰ると、妻もすでに断酒会に通うようになっていました。妻とは会話もないような状態でしたが、例会だけは一緒に行くことができました。そうして内外からじわじわと断酒への圧力がかかる中、私は追いつめられ、連続飲酒に陥りました。
最後の連続飲酒の後で
あの連続飲酒は、飲みたいという欲求とやめたいという気持ちの最後の闘いだったと思います。酒屋に電話をして、焼酎を5本頼み、取り上げたら殺すという気迫で飲み続けました。妻は断酒会で学んでいたので、何も言わず毎日仕事に出かけていきました。そして1週間目にもう一つの転機が起こったのです。
呼び鈴が鳴り、妻の妹の声が聞こえたので、フラフラと出ていくと、義妹は野菜を届けるため尋ねてきたと言いました。ところが玄関を開け、私の顔を見た瞬間、憔悴した様子に驚いたのでしょう、「どうしたの…」と言って泣き出しました。「兄さん、病院へ行こう」と言われ、「うん」と答えている自分がいました。あの瞬間、ようやく白旗をあげることができたのです。
翌日、妻と妹夫婦に連れられ病院へ行き、それが最後の入院になりました。最初の1ヵ月は離脱症状が続き、苦しみました。それでも体が楽になると、まだ大丈夫なのではないかという気持ちが出てきました。自分は依存症なんだと認めることができたのは、病院内での当番で洗面所を掃除しているときでした。流しの底に溜まっていた米粒を見て、「依存症者は歯が悪い」と医師が言っていたことを思い出したのです。自分も歯を磨くと、こんなふうに歯に詰まったものを出している……。入院している人たちが依存症で、こうやって歯に米粒が詰まるのなら、自分もやっぱり依存症なんだという考えがすーっと出てきました。その日を境に院内例会や自助グループに熱心に出るようになり、酒がピタリと止まったのです。
弱さを認めることは、人を強くする

依存症は「生き方の病」とも言われます。何度も例会で体験を話すうち、私は自分の弱さを補うために酒を飲み、また弱さから逃げるために飲んだのだとわかりました。私は長い間、自分がアルコール依存症であることを頑なに否認してきました。団塊の世代に生まれ、他と競うことを叩き込まれた私にとって、弱さを認めることは負けを認めるようで怖かったのです。けれども依存症であることを認めたら、断酒会という温かい居場所ができて、酒が止まりました。弱さを認めることは、人を強くするのです。
そのことがわかったら、今まで逃げたりごまかしてきた自分の現実と向き合おうという気持ちがわいてきました。自分がアルコール依存症であること、人間関係の中で起こる気持ち。それは苦しいかもしれないし、楽しいかもしれない。つらいかもしれないけれど、せっかく酒をやめたのだから、全部味わってみよう、と。
子どもの結婚が決まり、結婚式で親族固めの杯が飲めないことを相手方の両親にどう伝えようと悩んだときも、荒っぽいかもしれないが正直にアルコール依存症だと伝えようと決めました。私は一度隠したら、隠し通すため、それが負担になっていくと思ったのです。もし私が依存症であることが原因で子どもが不利になることがあったとしたら、それは私の問題ではなく相手方の問題だと自分を勇気づけました。伝えてみたら変な顔をされることもなく「そうですか」と受け入れてくれ、とてもホッとしました。職場でも思い切ってみんなの前でカミングアウトしたら、宴会の席に出なくても咎められることがなくなりました。
飲んでいた頃は、こんなことを言ったら相手はどう思うだろうと不安で、思ったことを言わないことが多くありました。けれども私にとって、話すことはとても大切です。酒をやめてから、自分を隠さずにいることの楽さを知りました。自分はこれ以上でもこれ以下でもない人間だと思うと、ありのままの自分でいられるのです。
- 回復のカギ
- ●断酒会員との出会い
- ●義妹の泣き顔
- ●病院の洗面所の米粒
※写真は本文とは関係ありません