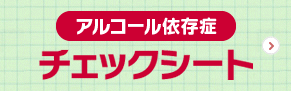回復のカギ
社長就任式で手の震えがバレて、退任。それでも自分が「アル中」だとは、どうしても認められなかった。
Y・Y 断酒10年(男性・70歳・元不動産会社取締役)
手の震えを必死でごまかしてきたが……

私は56歳のときに精神科でアルコール依存症と診断され、60歳で専門病院に入院しました。最近になって、最初に精神科につながったときのことで意外な事実がわかりました。私の記憶では、妻に無理やり連れて行かれたと思っていたのですが、妻は「あなた、自分から頼んだのよ。手の震えを止めてくれる病院に連れて行ってくれって」と言うのです。アルコール依存症は、否認の病とも言われます。依存症者にとって酒が飲めなくなることは最大の恐怖なので、私は自ら助けを求めながらも、否認が働き「無理やり連れて行かれた」と記憶まで摩り替えたのかと思い、改めてこの病気の深さを知りました。
当時、私は手の震えで悩んでいました。特に50歳を過ぎた頃からひどくなり、居間で新聞を読んだり食事をしているときに、子どもにも「お父さん、新聞が揺れてるよ」「お箸が揺れてるよ」と指摘されていました。それまでも妻には「1週間に1本という約束のボトルがもうなくなっている。酒屋さんに行くのが恥ずかしいからやめてください」と再三言われていたし、酒に問題があることは薄々気づいていましたが、怖くて考えないようにしていました。酒は飲みたいが、手の震えは怖い。飲むと手の震えが止まるのは、もっと怖い。自分に何が起きているのだろうと思うとすごく不安で、1杯の酒が重く感じられました。
仕事では字が書けなくなり、それを隠すため、取引先との契約でも部下を連れて行きサインを任せたりし、あれこれ工作をしないとままならなくなりました。そんな状態の中、会社の合併があり、私は新会社の社長に就任しました。ところが就任式では、他の人にサインを頼むことなどできません。結局、手が震えていることが公になってしまい、次の取締役会で早々に退任させられてしまったのです。「過去の功績もあるから取締役相談役に」とのことでしたが、机がぽつんと置かれた小さな部屋に連れて行かれ「今日からここが執務室です」と言われたときは、これで自分は終わったと思いました。
手の震えはますますひどくなり、コップも片手で持つとこぼれてしまう状態でした。両手で持っても震えて口まで持っていくことができず、口を近づけて飲もうとすると半分以上はこぼれてしまうという有様でした。それでも精神科クリニックにつながり、「アルコール依存症」と伝えられたときはショックでした。自分はアル中なのか? アル中は道路に大の字になって寝転ぶような人のことではないのか? 自分は違うと頑なに否認しました。
入院プログラムで初めて希望を見出した
このままでは限界だと感じたのは、それから4年後のことです。その間、通院し、自助グループにも通っていましたが、どうしても「ここは自分のいる世界ではない」「ここにいる人たちと自分は違う」という意識があって、「節酒」という名目で飲み続けていたのです。けれども断酒会の全国大会である家族の体験談を聞き、衝撃を受け、自分が間違っていたことに気づかされました。どうにも苦しくて、断酒会で「今まで自分はずっと嘘をついていました。専門病院へ行って一からやり直します」と宣言し、自ら入院したときは「これでやっと酒から逃げられる」という思いだけでした。
入院プログラムでは、脳のCTスキャンや画像を使った依存症の説明や、アルコールが身体に及ぼす害についての講義を受け、自分の病気を客観的に知ることができました。断酒会の家族が体験を話してくれる時間では、家族がいかに苦しんでいるのかに気づかされました。自分の苦しさだけに目が行き、家族の苦しみを知ろうともしていなかったのです。そして私にとっていちばん良かったのは、認知行動療法でした。
それまでの私は、飲んでいても、手の震え以外は仕事がきちんとできていたと思っていました。しかしそれは間違えで、実際はとんちんかんなことをしたこともあったし、何度も夜に電車を乗り越していたし、そのときに利用する常宿までありました。普通ではそんなこと、考えられません。また「3年先、5年先のあなたを考えてください」というワークでは、初めて希望を見出しました。依存症と診断されて以来、絶望的な気持ちを覆い隠すのに必死で先のことなど何も考えられなかったのですが、こんなこともしてみたい、あんなこともしてみたいと考えたらとてもわくわくしました。ずっと酒でいっぱいだった頭が断酒して空っぽになったのだから、そこを未来で埋めればいいと感じられたのです。
家族との温度差を縮めながら

あれから10年。今も夫婦で断酒会に通う生活を続けています。他愛のないことですが、たとえば花や景色を見てきれいだと感じ、そんな自分に驚くことの積み重ねだったように思います。飲んでいたときは、グラスを通して世界をみていたような感じで、どこかぼけたりかすんだりしていました。酒はその人の視覚や思考を歪ませるのだと改めて思います。
妻や他の家族の話に耳を傾けるようになったら、冒頭のような記憶や思考の歪みもわかるようになりました。たとえば私は断酒会で体験を語る中で、「そもそも晩酌の習慣は妻が持ち込んでくれた」と表現していたのですが、あるとき妻に「それは全然違う!」と言われました。私は自分の両親が酒を飲まなかったので、晩酌の習慣がある家庭で育った妻が何のためらいもなく晩酌を準備してくれてよかったと思っていたのですが、妻にすれば「あれだけ飲んで帰ってきて、酒、酒という人に出さないわけにはいかなかった」と。妻は私が気づくより何年も前から、私の酒のことで悩んでいて、あちこちに相談をしていたのです。
今になって思い返せば、最初に精神科につながったときも、妻だったらどこへ行けばいいか知っているのではないかとどこかで考えていました。いつの頃からか、私の酒に関してピタリと何も言わなくなり、それは妻が断酒会に通っていろいろ対応を学んだからなのだと後になって知りました。どんなに飲んでもきちんと生活できていると思っていたのに、それができなくなったと感じたのもその頃です。玄関で寝ていたり、背広のまま寝ていたり。実はそれまでは、妻や子どもが、正体不明になった私を部屋に引きずり上げ、寝巻きに着替えさせて布団に寝かしていたのです。私はそれに気づかず「俺は酒を飲んでもちゃんとしている」と錯覚していたのでした。
これからも、こうした記憶や思考の歪みをいろいろと発見していくのでしょう。依存症者本人と家族の認識の違いは、とても大きなものだと実感します。家庭にしても、酒をやめたからといって元通りになるというものではないので、新しい家族の形を作っていくことが大切なのだと思います。妻との関係は、以前は「亭主とかみさん」という従属関係のようなものでしたが、今は少しずつ「同志」になってきたように感じます。妻のことを「おいおい」とか、「お母さん」としか呼んでいなかったのに、名前で呼ぶようになり、何かあったときもお互い「あなたはどう思う?」と聞いて、話し合うことができる関係です。依存症という病気は、どんなにやめていても一杯飲めば元に戻ってしまうやっかいなものではありますが、これからもこうして自分のあり方を変え続けていきたいと思っています。
- 回復のカギ
- ●断酒会
- ●認知行動療法
- ●妻・家族の支え
※写真は本文とは関係ありません